ちょっとだけ紅葉お散歩
先週は屋久島に行っちゃったりして植物成分はもう十二分に吸収したのですが、紅葉がまだだったのと家族サービスで川崎市生田緑地に散歩に来てみました。

初めて来てみたのですが結構広いですね。
そしてアップダウンもそれなりに。。。

肝心な紅葉の具合はと言いますと、モミジは今一つ紅葉しきってない感じ。
樹が丸々紅く染まっているのは種類が少し違いそうでした、カエデの仲間ですかね。。
僕としては緑の葉と紅い葉、そして中間の黄色といったグラデーションが好きなのでモミジがちょうど良い具合でした。
モミジやカエデだけではなく、ヒマラヤスギが群生で高く伸びて黄色く色づいた葉から日差しが透ける場所がすごく綺麗で良かったです。
生田緑地の敷地内には日本民家園も併設されており、こちらもちょっと覗いてみました。
日本民家園では各地の古い民家を保存のために移設して公開しています。
古い土間や囲炉裏のある民家が立ち並び、いくつかは中に入ったり上がることができたりするものもあります。
しかし藁葺きの古い日本家屋ってなんとなくですが雪が似合いそうだなと感じるのはなんなんでしょうかね。
大雪の降る中で藁葺き家屋に宿泊、なんてのやってみたいですね笑
散策できる山道やのんびりお弁当を広げられる公園もいくつかあって子供連れで遊びに来るにはすごく良い場所だと思います。
まだぎりぎり紅葉なども間に合うと思うのでお近くの方は是非訪れてみてください。
久島(縄文杉)へ行こう 〜行っちゃう編〜
現実から目を背けたりなんだかんだしてますと気づけば長らくブログを放置しておりました。。。
毎日更新とまでは言いませんが、さすがにこれほど開くのはよろしくないですね、反省いたす次第です。
ということでお休みしていた間にちゃっかりと屋久島に行ったりなんかしていたわけです。

計画は前回ご紹介したような感じで予定していました。
行程としては2泊3日で宿は民宿、初日は素泊まりで夕食は外で食べ、登山をした2日目は疲れもあるだろうという予想で晩御飯を付けました。
ちなみに宿は安房地区にある「つわんこ」さんにお世話になりました。
露天風の温泉が疲れた体に優しく、宿の方も非常に気さくで良いお宿でした。
*初日 ~到着~
僕らは同行者の都合で、夕方に屋久島に着くフェリーで到着したので着いたころには陽も落ちてさすがにその日はできることはなく居酒屋へ直行。
屋久島名物の首折れサバや飛び魚を始めとした刺し盛りはさすがの一言。
そして同じく屋久島名物の焼酎三岳、そりゃあお酒も進みます。
*2日目 ~登山~
というわけで軽い二日酔いを引っ下げ登山に臨みます。
良い子の皆は登山前日のお酒はほどほどにな⭐️
朝5時に宿を出発し、荒川登山口から出発します。
しばらくは割と平坦なトロッコ道をひたすら歩きます。
ちなみにこのトロッコは現役で荷物の運搬等に使用されることがあるとのことで、今日は来ないと思うけど轢かれないでね〜と近くにいたガイドさんも言っていました。
ちなみに僕らのグループは経験者もいたのでガイドさんはお願いしていなかったのですが、屋久島の場合は動植物や歴史的背景も豊富なのでガイドさんがいたほうがより楽しめるかもしれませんね。

トロッコ道を終え、屋久鹿や猿との遭遇を経ながら突き進みます。
ちなみにトロッコ道はかなり緩やかですが結構長く、体感で5分の3くらいかなと感じました。
それが終わると本格的な山道に入りますが、こちらは場所によっては急勾配でキツくなってきます。
それと同時に周囲も苔生して大木や倒木も増えてきて如何にもといった雰囲気が出てきます。
屋久島の独特な魅力を支えているのはなんと言ってもこの苔ですよね!
折しも小雨パラつく天気だったのでこのウェッティな程よい苔具合を堪能できました。
そうこうしているうちに本命である縄文杉に到着です。
やっぱり神々しさは群を抜いていますね。
雨が降ったことで少し霧がかってますがそれがかえって妖しさというか色っぽさを出しています。
帰りはのんびりと川べりを覗いたりしながら戻ります。
さすがに川の水もかなり綺麗で夏なら飛び込みたくなるような透明度でした。
そうこうしてるうちに下山となりましたが、僕らの一行はだいぶのんびり行っていたので往復で約10時間かかっていました。
年齢等を考えたらもっと早くてもいいはずですが・・・まぁそこは屋久島を味わいながら行ったということで笑
ともあれ無事で何よりです。
*3日目 ~オマケ~
予定では3日目はのんびりして帰るつもりでしたが、2日目の夜に様々なガイドをしている宿のご主人と盛り上がり、カヌーを体験するという運びとなりました。
半日ということであまり奥までは行っていませんが周りを深い緑に囲まれた場所でのカヌーは完全に忙しない日常を忘れさせ、現実世界から引き離すには十分すぎる魔力を持っていました。。
これで晴れた夏の日だったら完全にアウトでしたね。
そんなこんなで結果的にかなりイベント詰め詰めの屋久島旅行になってしまいましたが、屋久島の山は何度登っても最高ですし、初めてのカヌーも思った以上に気にいってしまいました。
結果オーライな部分もありましたがほぼほぼ100点満点な旅行となりました。
「いつか一度は」と思っているアナタ、これを参考に冬が明けたら是非行ってみては。
屋久島(縄文杉)へ行こう 〜準備編〜
いきおいで付き合いの長い友人たちと屋久島に行くことになりました。
僕は5年ほど前にも行ったことがあり、今回も予定組みを仰せつかりましたので備忘録がてらまとめておこうかと思います。

メジャーな縄文杉やもののけの森で知られる白谷雲水峡(上の写真)を回るコースをカバーしてますので、いつかなにがしかで行ってみたいと思っている方は参考にしてもらえればと。
【日程編】
縄文杉を見る場合、一般的なルートである<荒川登山口~縄文杉>の往復は約10時間が目安タイムとなっています。
登山道ルートについては以下の資料を参照してください(緑のコース)
http://yakukan.jp/doc/pdf/tozancourse.pdf
出発は早朝、戻りは夕方頃となりますので前後に移動日をとって2泊3日が最低限必要になってきます。
個人的にはベストシーズンは5,6月かなと思いますが、ベストシーズンは結構混みますのでその辺も考慮したほうが良いかもしれません。
僕は以前は6月に行きましたが、場所によっては結構渋滞していました。。
ちなみに12~2月は積雪のため急激に難易度が上がります。
冬山慣れした猛者以外は止めておきましょう。。
以下の環境省のサイトにおおまかな混雑状況が紹介されてます。
宿探しなどにも影響しますのでまずは参考にしてみてください。
※補足
先に挙げた<荒川登山口~縄文杉>のルートでは縄文杉・大王杉・夫婦杉・ウィルソン株といったポイントを見ることができます。
「もののけの森(白谷雲水峡)も一緒に見ることができるか」という質問をよく目にしますが、よほど体力に自信のある方でないとオススメできません。
縄文杉から白谷雲水峡へは分岐ポイントからルートを変更すれば行くことは可能ですが、登山口へのマイカー規制がかかっているおり、最終バスに間に合わないとさらに長距離を歩くハメになります。。。
目安としては週2,3回運動をしている20代前半男性の体力でギリギリ、というところです。というか僕がそうでした。
白谷雲水峡は登山口となる白谷広場から往復3時間ほどが目安タイムなので初日に組み込むのが吉です。
【屋久島までの行き方】
屋久島への飛行機直行便は鹿児島・福岡・大阪から出ています。(JAL)
もしくは鹿児島からフェリーで行くことも可能です。
フェリーの場合は鹿児島から約2時間の高速船トッピーか、約4時間のフェリー屋久島2を選択することになります。
まぁ当然というかトッピーのほうがいささかお値段上がりますね。
ちなみに鹿児島空港からフェリー乗り場までは高速バスで約1時間ほどです。
県外の方で時間に余裕のある方は鹿児島も楽しんでみてください。
※補足
屋久島のフェリー乗り場には安房港と宮之浦港の2箇所があります。
どういう登山ルートにするか、どこに宿を取るかで判断してください、そこそこ離れてます。
ちなみにフェリーはどちらか片方の港にしか着きませんので時刻表の確認時に注意してください。
【宿&食事について】
屋久島には大小様々な宿があり、ネットで検索してもホームページを持っていないような宿もあります。。
が、以下の屋久島観光協会のサイトにかなり網羅されていますのでこちらを参照すればハイシーズンに出遅れない限りは大丈夫でしょう。
宿を探す時は登山口に近い地区を選んだほうがよいでしょう。
縄文杉(荒川登山口)なら安房、白谷雲水峡メインなら宮之浦、といった具合に。
ちなみにこちらの観光協会のサイトでは屋久島の飲食店や公共交通機関、地図などのかなり充実した資料が公開されています。
屋久島に行く予定の方は必携ですね。
縄文杉登山に行く方は早朝出発になりますので予約時に宿の方にその旨を伝えて登山弁当の手配についても相談しましょう。
宿で用意してくれるところとお弁当屋さんを紹介されるケースがあります。
登山とはいえ旅行メシはお楽しみ。
宿で食べるなり、近くのお店で楽しんでください。
【まとめ】
とまぁこんな感じで予定が組み上がってくるんじゃないでしょうか。
予定は未定のほうが楽しいじゃないという趣もあるとは思いますが、登山で結構長い時間歩いて疲れますのである程度予定を組んでおいたほうが後々楽かなとも思います。
決めておくことは決めておき、その場で対処できる余裕も合わせて作るくらいが楽しいんじゃないでしょうか。
というわけで今回はここまでー

竹灯篭の静かな夜を
先日のエントリでも軽く触れましたが、昔の写真をGoogle Photosに移行しております。
そんな中でふと目にとまったイベントをご紹介したく。
街中に竹で作った灯篭が設置され、日が暮れてから一斉に中のろうそくに点火します。
すると竹の切り口から優しい光が漏れて幻想的な雰囲気を作ります。
元々夜ですし、ろうそくの小さな火が揺らめく静かな街中に、歩く見物客の楽しそうな話声だけが広がります。
すごく穏やかで楽しいお祭りです。
僕が行ったのは2009年と大分昔ですが、今もお祭りは行われており、そう大きな変化はないのかなということで当時の写真をちょっとご紹介。
昼間から準備は始まっています。

日が暮れると一気に点火されます。

竹灯篭が街を埋め尽くします。

優しい光が溢れます。

ちなみに今年は11月20~22日で開催とのことですのでお近くの方は是非行ってみてください。
お近くでない、という方も調べてみると全国的に結構色々な場所でやっているようです。
今年はすでに終わってしまったものも多いようですが、来年用に考えてみては?
・神奈川県 横浜国際プール竹灯籠まつり →今年は10月4日に終了
・神奈川県 藤沢市 龍の口竹灯籠 →今年は8月1日に終了
・神奈川県 小机城址市民の森 竹灯籠まつり →今年は10月24日に終了
・静岡県 韮山 竹灯篭まつり →今年は11月14,15日に開催予定
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kankou/jidaimaturi/documents/taketouroutirasi.pdf
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/kankou/jidaimaturi/documents/taketourourimen.pdf
いつか見返す日のために、何かの記録は残しておいた方がいいですよというお話
最近ちとブログ更新をサボり気味です。。。
というよりはちょっと自分の過去記事を見直して、ちょっと思うところもありましたので無理して毎日更新を優先しないようにしてみます。
「読んでくれる皆さんはもちろん、数年後に自分が見ても楽しめるエントリーを」
というのを追ってみようと思います。
当然やっつけのエントリーなんて自分が読んでも面白くないですからね。
そんな当たり前のことに気づいたのは写真の整理がきっかけでした。
以前にもエントリに書いたGoogle Photos、しばらく使ってみてやはりコイツはいけそうだってんで本格的にこれまでの写真をGoogle Photosに移してバックアップストレージとして運用しようと思った次第です。
あ、バックアップはこれだけじゃないですよ、二重三重が鉄則ですからね。
というわけで外付けHDDに保存してある数千枚の写真の内、消えたら特に困りそうなものをGoogle Photosへどんどん移します。
PCで作業して、スマホからも写真が見れるようになるってのは良いですね。
僕が写真に興味を持つようになったのが10年前にワーホリでカナダに行った時からなので、約10年分の写真があるわけです。
全部とは言いませんがどんどん移していきます。
まさか常に持ち歩いているスマホで10年前に撮ったくだらない記念写真がいつでも見れるような時代になるとは・・・
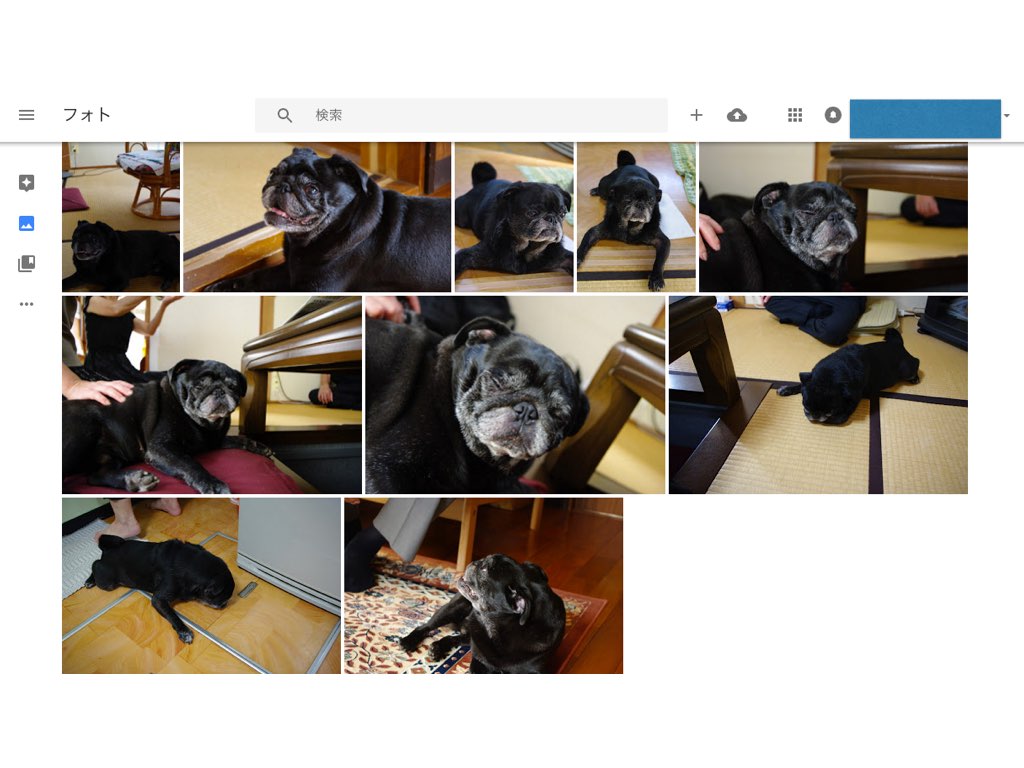
これはくだらなくない、親戚の家で飼っていたパグですね。
実はこのキャプチャの中に2匹いるんですがまったく見分けがつきません笑
この子らも2,3年前に大往生して天国へと旅立ちましたが、こうするといつでも見ることができます。
こうして昔の写真を見返しているとそれはそれは作業の手は止まるわけで笑
枚数が多いこともありますがまだ作業が終わりません。。。
ただ、やっぱりこうして見返すと写真撮っておいて良かったなぁと。
そしてバックアップだなんだに気を配りながらも保存しておいて良かったなぁと思います。
こうして振り返るための手段ってのは何も写真に限らないと思うんですよね。
紙の日記でも、ブログでも。
今考えていることを反映させながら、日々ちょこちょこと積み上げていって後から見返せるカタチにすることができたなら。
そんなわけで毎日ではなくとも、そんなに面白い事書けなくとも、ブログは書き続けたほうがいいなぁと改めて思った次第でした。
※Google Photosも今は気前の良い使用条件ですが、One Driveの件もありましたので過剰な容量使用には気をつけましょう。。
鼻うがいはすごく楽になるよ
ちょいちょいホッテントリでもお見かけする「人生いつも三日ボーズ」さんでどうしてもスルーしたくないお話があり、キーを叩く次第です。
他の方のブログに直で言及するのは初めてですが、あくまでも「こうしてみては?」というサジェストですのでどうかお気を悪くされないでいただけると幸い。
さて、掲題の記事は「風邪が辛いから鼻うがいしたけど適当にやったからキツかったわ」ということなようなのですが、まずは風邪っぴきとのことでお見舞い申し上げます。
そして、僕も鼻うがいは得意ではない人間ですので心中お察し致します。
とはいえ上を向いてシャワーは・・・・ちと無理しすぎっす・・・
しかしながら鼻うがいは常々「鼻を取り外して洗えないもんか・・・」と思っていたアレルギー鼻炎持ちの自分としてはオススメできる家庭療法の一つですのでもうちょっと上手くやる方法を三段階でご紹介させてください。
ちなみに鼻うがいは上手くやると鼻づまり等の症状がかなり楽になります。
鼻うがいはやり方を間違えると中耳炎なども引き起こしますので、例によって自己責任でお願いしますね⭐️
1. まずはコップで鼻うがい
生理食塩水程の濃度に食塩を溶かしたぬるま湯をコップに注ぎ、鼻の片方の穴からそれを吸いこみ、口から出すというシンプルな方法。
これができる人は初期投資もいらないので最も良い方法と言えるでしょう。
ちなみに僕はこの方法でやると普通に飲み込んでしまってむせてダメでした。。。
2. 鼻うがい補助道具を使ってみる
鼻で吸う→口から吐くという動作が苦手な人のために、鼻へ生理食塩水を流し込んでくれる小さなジョウロというか、スポイトのような補助道具がいくつかのメーカーから販売されています。
手で食塩水を押し出すようにして鼻の中に流しこめるので、1ができない人でもこれならばという人もいるようです。
ちなみに僕は小林製薬さんの「ハナノア」を試しましたが、やはりそのまま気管へ・・・
自分はここまで不器用な人間だったかと少し凹みました。
製品レビューを見るとこれで上手くできるようになったという人も多いようでした。
ちなみにこれで上手くいく人は次に紹介する最終兵器よりも小さいのでどこへでも持ち運べるので良いですね。
3. 最終兵器 耳鼻科っぽいモノを導入する
前述の2つの方法を試しましたが、残念ながら僕にはいずれも壁の高い技術だったようです。
そんな絶望の淵に立たされた僕はついに最終兵器を投入します。
僕はこれを試してようやく鼻うがいに成功しました。
2で紹介したハナノア同様に鼻に食塩水を送り込んでくれる装置なのですが こいつはスバラシイ。
ちょっと調べたところ、2のタイプと違ってまだあまり競合は出ていなさそうです。
ハナノアとの違いとしては
①圧倒的水量:食塩水の容量が300mlと大容量なので鼻水は完全に流されます
②暴力的水圧:暴力は言い過ぎですが、押し出し手動ポンプのため水圧も少し強めなのでかえって自分が調整する必要なく出てきます。
というわけで 「鼻うがい奮闘記」をお送りしてきましたがいかがでしたでしょうか。
僕はこれらのトライアンドエラーにて心強い伴侶(ハナクリーンEX)を得ることができましたので、それ以降はちょっと怪しい時はすぐに鼻うがいで早めの対処を心がけています。
というよりも冒頭のヨシキさんのように僕も今週風邪気味でしたが、この鼻うがいハックによりある程度で止めていた次第。
風邪気味、鼻炎、花粉症等で鼻・喉の不調にお悩みの方は鼻うがい、本当に楽になるので是非お試しください。
※繰り返しになりますが、鼻うがいはやり方を間違えると別症状も引き起こしますので別文献等もお調べの上、自己責任にてご実施ください。
お気に入りの紅葉スポット ~光明禅寺~
なんとなーく避けていた「今週のお題」ですがついに乗っかってみようかと思います。
べ、別にネタが尽きたわけじゃないんだからね!
ふと今週のお題である「お気に入りの紅葉スポット」というのが目に入り、はたと思い出しました。
九州唯一の枯山水でも知られる福岡・大宰府の光明禅寺の紅葉が美しいのです。
光明禅寺は、学問の神として知られる太宰府天満宮から歩いてすぐの距離にあり、西鉄大宰府駅から大宰府天満宮を結ぶ参道のにぎわいから少し外れた所にひっそりと佇んでいます。
外観からして歴史を感じさせるお寺は外壁も一部剥がれて土色がむき出しになっていますが、その外壁から覗く紅葉がついつい中へとひきこんでくれます。

中庭には水を使わず風景を表現する枯山水が広がり、大海を表現した白砂が優雅に流れています。
陸を表現している青苔は、別名で苔寺とも呼ばれるこのお寺のシンボルマークの一つにもなっています。
初夏の時期には苔が瑞々しくてすごく趣がありますが、白・緑・赤・黄と様々な色を味わえるこの時期もまた荘厳な世界が広がっていて一見の価値があります。


実際には僕が最後にこのお寺を訪ねたのは学生時代が最後なので7,8年程前のお話になりますが、初夏とこの時期と年に2回、それもかなり独特な写真映えする場所でお気に入りだったので何度か通いました。
人混みを避けるためになるべく朝早く行くとこの時期でも結構寒く、震えながら写真を撮って、帰りに焼き立ての梅ケ枝餅を食べた記憶があります。
焼き立ての梅ケ枝餅は最強です。
個人的な感傷はさておいたとしても、駅からほど近く、大宰府天満宮や九州国立博物館といった王道の見どころもたくさんありますのでお近くの方、福岡へ行く機会のある方は是非訪れてみてください。